ゼロトラストの周辺
バズワードとしてのゼロトラスト
最近のセキュリティ関係のセミナーでは、「ゼロトラスト」というワードが必ず出てくる。1年程前までは、言葉ばかりが先行して、肝心の中身は、コロナ下ということもあり、大手企業に向けて、かなり高額なサービスという印象だった。
アーリーアダプターの方々の人柱のおかげか、技術要素の整理も進み、IPAからも「ゼロトラスト移行のすゝめ」などという文書も出てきた。
ゼロトラストの全体図としては、以下が分かりやすい。
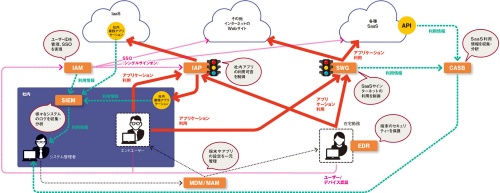
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/01311/052200002/ から引用。
上記内容は、以下の書籍にまとめられている。
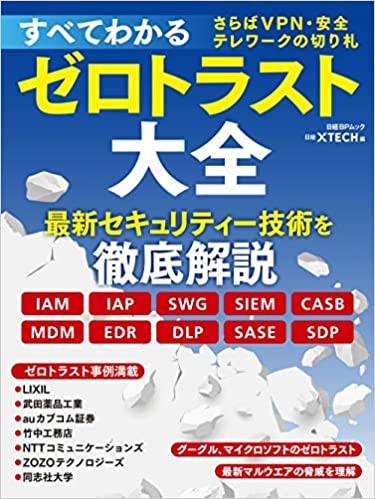
まず、表紙に書かれている3-4文字の略称が覚えられず、苦労する。
IAM:アイデンティティ&アクセス管理
SWG:セキュアWebゲートウェイ
SIEM:セキュリティ情報イベント管理
CASB:クラウド・アクセス・セキュリティ・ブローカ
MDM:モバイルデイバス管理
EDR:エンドポイント・ディテクション&レスポンス
DLP:情報漏洩防止
SASE:セキュア・アクセス・サービスエッジ
SDP:ソフトウェアで定義された境界
書籍の中で、具体例などを用いて、説明されており、理解が進んだ。
上記概念が全て提供されているサービスはなく、ベンダーで個別に提供されていたり、複数の機能を併せ持つサービスも提供されていて、混沌としている。
さらに混乱するのが、EDRやSDPなど、似た概念が増えていること。
EDR(EndPoint Detection and Response)周辺
EDRは、
EPP(Endpoint Protection Platform:従来のウイルス対策ソフト)や
NGAV(Next Generation Anti Virus:NGAVは次世代アンチウイルス)
では守れきれなかった場合に、隔離・根絶・復旧までを行う仕組み。
MDR(Managed Detection and Response)は外部の専門家のサポートを受け、EDRをはじめとしたセキュリティ製品によっていち早く脅威を検知し、インシデント対応をするためのサービス。
NDR(Network Detection and Response)とは、ネットワーク上のさまざまな情報(ログ)を収集し、分析することで危険なものを検知するソリューション
XDR(Extended Detection and Response)とは、EDRの機能を拡張することで、エンドポイントだけでなく、ネットワーク、アプリケーションスイート、ユーザーペルソナ、オンプレミスのデータセンター、クラウドでホスティングされているワークロード全体を通じて、サイバー攻撃の検知と防止を実現できるようにするセキュリティアプローチです。
米調査会社ガートナーは、EDRとNDRとSIEMの3つを「SOC Visibility Triad」として、重要な組み合わせであるとしています。
SDP(Software Defined Perimeter)の周辺
SDPは、集中的なアクセス制御を「ソフトウェア」で実現することで、物理的な境界では防ぎきれない脅威の防御を可能にする仕組み。
サーバーの仮想化では、以下の単語が出てきた。
SDC:Software Defined Compute
SDS:Software Defined Storage
SDN:Software Defined Network
物理的なリソースを仮想化して、ソフトウェアで制御する
上記以外に、
SDDC:Software Defined Data Center
SDI:Software Defined Infrastructure
SD-WAN:Software Defined Wide Area Network
など、もう少し広い概念となる。
SDP≒ゼロトラスト、と言える気もするが、やはり、ゼロトラスト、という曖昧な概念でなければ、包括的な考えとして、全体を網羅することは難しいのでしょう。